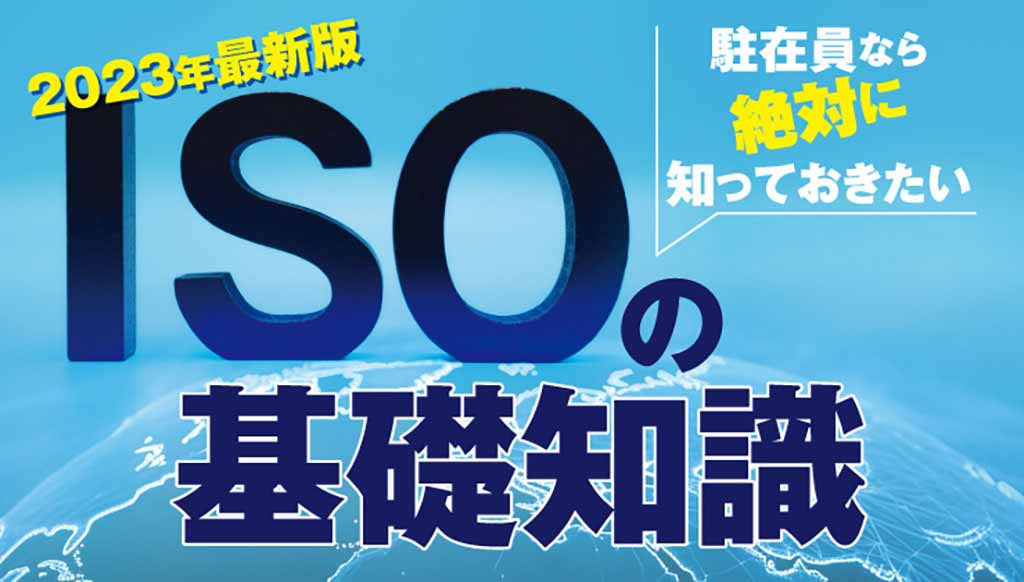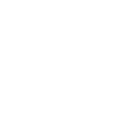ISOとは、スイスのジュネーブに本拠地がある国際標準化機構のこと。国際標準化機構の英語表記は「International Organization for Standardization」。
では、国際標準化機構とはその名の通り、世界の標準(規格)を決める団体のこと。例えば案内標識や看板、長さや質量、時間を表す単位、そして身近なところではコンセントやプラグなどの規格が挙げられるだろう。これらを国際的に標準化することで、世界中の人が便利な生活を享受できることになる。
また、食品など商品の品質やサービスをISOで統一化することで、安全・安心なものを消費者や顧客に継続的に提供することが可能だ。
このISOで「定められた規格で商品やサービスを提供している」かを証明するのが、ISO認証。ISOこれは、提供する商品の品質やサービスが水準以上であると認められたときに得られる認証証明書のことで、この認証証明書が発行されて手元に届いたときは一般的に公開することが可能。
タイで活動する日系企業によってもビジネスの鍵となるISO。
ここでは「国際間の取引をスムーズにするための共通基準を決める」などの目的を持って定められたISOの重要性や、取得するためのプロセスなどを紹介。駐在員なら知らなければならないISOの基礎知識を整理した。
- ISOの基礎知識
- 主なISO及びマネジメントシステムの種類と目的
- 日本企業がタイでISOを取得するべき理由とは
- ISO取得をタイ人に任せきりにするのはNG
- ISO認証は3年間を1サイクルとして持続していく
- 2023年 最新版 ISOの合言葉は「持続可能」と「サスティナビリティ」
- 鍵となるのは引き続き Sustainable(持続可能) Circular economy(循環型経済)
- ISOが Net-Zero Guidelineを発表
- ISO認証を利用して自社アピール まずはISO14001を受けることが鍵!
- 【ISO50001】とは
- 贈収賄防止を目的としたISO認証も必須!
- 【ISO37001】とは
- ISO認証マネジメントシステムの代表例
- 【ISO9001】品質マネジメントシステム
- 【ISO14001】環境マネジメントシステム
- 【ISO45001】労働安全衛生マネジメントシステム
- 【IATF16949】自動車産業向け品質マネジメントシステム
- 【ISO10002】苦情対応マネジメントシステム
- 【R2】(Responsible Recycling:リサイクル認証)
- 【AS9100】航空宇宙産業向け規格
- 【ISO13485】医療機器の品質マネジメントシステム
- 【GMP HACCP】適正製造規範
- 【FSSC22000】食品安全システム
- タイでも確実に広がる認証取得の流れ ISOを知っておくべき必要性
- ISO取得のプロセス
- 1. ISO取得の目的を定める
- 2. ISO審査登録機関に依頼
- 3. 認証登録審査
- 4. 登録の推薦・判定
- 5. 登録証の発行
- 豊富な実績と経験を持ち、すべて日本語で対応 ISO認証取得・更新を任せる 審査登録機関ならこちらへ!
ISOの基礎知識
主なISO及びマネジメントシステムの種類と目的
「国際間の取引をスムーズにするために共通の基準を決める」。そのような目的を持って定められたISOには、番号によって多くの種類があり、そのうちの「マネジメントシステム」規格は、いわゆる「組織の仕組み」を指す。このISOマネジメントシステムは「うまくいく仕組み」を構築する上で不可欠だ。
日本企業がタイでISOを取得するべき理由とは
文書一つを例にとってみても、タイ人と日本人の間には理解度に差があり、例えば技術関連文書にしても、タイ特有の書き方に適応した翻訳でないと理解されないことが多い。そこで、お互いの「理解のための根拠」として重要な役目を担うのがISOだとされている。日本でのやり方をそのままタイに持ち込み、なんとなくやり過ごしていくのではなく、しっかりとタイに根付き理想の事業を展開していく。ISO認証取得は、そのような場面において日本企業と日本人経営者のアドバンテージになり得るツールだと言えるだろう。
ISO取得をタイ人に任せきりにするのはNG
「ここはタイだからタイ人主体で」「事情をよくわかっているタイ人に自由にやらせたい」。ISOを取得する場合に、日本人は口出ししない方がいいとする経営者も多い。
しかし、タイ人に任せきりで体裁だけを整えていくというのは費用の無駄。組織が前進するための方向性などはもちろん経営者が主体となって決めていくことが大切だ。日本人が積極的にコミットし、現状を把握していくことでISOの価値が発揮され、事業を正しい方向へ導けると言える。内部監査などを通じて、経営方針に基づいて活動できているか、目標は管理されているか、コスト削減は出来ているかなどを随時把握する。経営者自らがこのような組織の方針に参加するための重要なツールの一つがISOなのだ。
ISO認証は3年間を1サイクルとして持続していく
ISOは認証取得したらそのままでいいかというとそうではない。3年間の有効期限があり、ISOのマネジメントシステムを継続的に活用するにはきちんと運用できているかを審査する必要がある。
ISO認証は、まず取得から1年後と2年後に「維持審査」があり、この時点で持続的に動いているかをチェック。さらに3年目には「更新審査」が行われる。つまり、ISO認証は3年更新になっていて、3年間を1サイクルとしながら繰り返して維持していくことになる。この1サイクルの間に実施される「定期審査」や「更新審査」もとより、自社内で行う内部監査も重要な項目だ。監査を通じて修正すべき点が見つかれば是正し、予防が必要となれば予防処置が必要になってくる。
以上のことから、ISO認証は取得時にだけコストがかかると思われがちだが、定期的な更新に伴ってコストが発生することも知っておかなければならない。
2023年 最新版
ISOの合言葉は「持続可能」と「サスティナビリティ」
鍵となるのは引き続き
Sustainable(持続可能)
Circular economy(循環型経済)
現在、経済界で引き続き旬となっているISOの合言葉は「Sustainable(持続可能)」 と「Circular economy(循環型経済)」 。これを受けるようにして、近年一般的に言われているのが3R(Reduce,
Reuse, Recycle)。この中のReuse(再利用)率は世界的にみても、8.6%という少ない数値に留まっていることが多方面で懸念されている。
そこでISO総会では、2021年9月に「ロンドン宣言」
を採択。今世界が直面している気候変動を、ISOの規格を活用することで「アジェンダ2050」の目標達成を支援する。環境に関して2024年までに既存の規格をテコ入れすることと、新しい規格の導入を計画しているところだ。
このような世界的傾向の影響で、今後は益々持続可能・循環型経済へのアプローチや対応が目に見える形となり、顧客の要求とともにサプライチェーンの中で厳しく要求される。各企業は顧客からの要求が来てから取り組むのでは、取り残される心配があるだろう。
国連主導のSDGs(持続可能な開発目標)についても評価・認証への動きが出てきていることから、年次レポート(環境報告書等)のような形でまとめて発表できるようにしておく必要が出てきた。
これからの企業活動にとって大切なのは、顧客の要求によって仕方なくISOの認証を取得するのではない。ISOの認証を使って自社のアピールをし、業績を上げて行く選択をすること。そのためのキーワードが、経営者が参画・主導するISO活動だ。
ISOが
Net-Zero Guidelineを発表
そのようなネットゼロ(カーボンニュートラル)が広まる時流へ乗るようにして、ISOはエジプトで開催されたCOP27に先駆けてNet-Zero
Guidelineを発表。2050年までに、ネットゼロを達成するための指南として以下のような目標を掲げ、マネジメントシステムを通してこれらを達成できるように奨励している。
- 排出の削減 (再生可能エネルギーへの乗り換え)
- カーボンオフセット (他社からGHG排出クレジットを買う)
- 透明性と説明責任 (排出量の第三者の検証)
- ステークホルダーの参加 (サプライチェーンを巻き込んでの活動)
したがって現在急務となっているのは、ISO14001環境マネジメントシステムを使い、環境側面・環境負荷を理解しながらそれらの低減活動を開始すること。そしてISO50001
エナジーマネジメントシステムを導入して省エネ対策を行い、環境に貢献することだ。
さらにISO14064 で温室効果ガス(GHG)排出量のモニタリングを行い、様々な省エネ活動を通してどの程度CO2の削減に貢献しているかを数値化して世界に発信することが必要となっている。