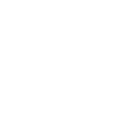駐在員におすすめ!香港の貯蓄型生命保険とは?
タイを含めた海外在住者は日本のつみたてNISAなどの優れた制度に新たに投資をすることができません。また日本の金融サービスを利用した投資信託や株式などへの投資にも制限があります。
海外居住中は日本の金融サービス利用に制限がかかるため、資産運用を行うことが困難になる場合もあります。
一方で、日本在住者は契約に制限のある海外の貯蓄型生命保険で資産運用ができるのは大きなメリットです。
なかでも、カナダ系大手保険会社のサンライフ香港が販売している米ドル建て貯蓄保険「SunJoy」はタイ在住の日本人のお客さまから多くのご契約いただいている商品のひとつです。
保険料のお支払い・保険金のお受け取りは共に日本、タイのどちらにお住まいでも手続きできます。
また、保険料は50,000USD、100,000USDなど、まとまった資金で契約をすることもできますし、月々250USD(約8,700THB)、積立期間も5年間など少額から始めることも可能です。
香港貯蓄型保険には多くのメリットがありますが、今回はその中から2つご紹介します。
1つ目のメリットは複利で資産を増やせることです。
機関投資家である保険会社は10年を超えた安定資産を契約者へ提供するために超長期の債券と流動性の高い株式で運用を行います。
また、保険会社は豊富な資金で運用を行いますので契約者へ複利を提供することができます。
例えば、35歳の男性が保険料50,000USDを全期前納した場合の予定解約返戻金は45歳時点では70,044USDですが、55歳時点ですと139,708USD、65歳時点では275,450USDと複利で資産が増加していきます。
2つ目のメリットは自由な資金の取り崩しです。
先ほどと同じく、35歳の男性が保険料50,000USDを全期前納した場合、65歳から100歳まで、仮に毎年19,000USDを引き出したとしても、100歳時の予定解約返戻金はまだ243,645USD残ります。
香港貯蓄型保険は市場の変動に一喜一憂することなく、老後に安定した年金資産を作ることができます。
また、途中で子どもなどに名義を変更して代々資産を継承することもできます。
以前は香港まで行かないと契約できませんでしたが、現在はタイにいながら郵送で契約できます。
どのようなリスクや注意点がありますか?
1つが流動性リスクです。例えば「SunJoy」は1年目で解約をした場合、戻ってくるのは25,540USDとなり元本割れをします。
ご契約から6年経過までは元本割れがほぼ確定しています。
10年以上は置いておける資金で契約することをお勧めします。
香港貯蓄型保険は運用期間の長さが資産を増やす重要な要素となります。近い将来に使う予定がある資金や生活を無理してまで行う投資ではありません。その時だからできる家族との旅行や将来の自分のために投資を行う方法もあります。それらを我慢してまで契約することはお勧めしません。
2つ目は為替リスクです。米ドル運用なので、その時の為替によっては米ドルでは増えていても差損が出る可能性もあります。
ただし、香港貯蓄型保険は運用期間の長さで保険金を増やしていきますので、為替のタイミングを見て投資を行うのではなく、運用期間の長さを重視して元の保険金を増やした方が有利になるケースもあります。
その他、注意点としては保険金受取時の税金です。
日本では保険金の税金は総合課税で計算をします。解約金の受け取り時に給与などの収入があると課税所得は合算され税金が高くなる場合もあります。
急な出費など偶発的に保険金を受け取ると一時所得、年金で受け取ると雑所得、奥様などに名義変更をした後に引き出しをした保険金は贈与税で計算をします。
あらかじめ税金の理解をしておくと香港貯蓄型生命保険は、他の金融商品よりもメリットとなる場合もありますので、ご契約前に税金の理解もしておくと良いでしょう。
税金についての詳細は弊社の公式LINEなどでも情報を発信しています。
香港の貯蓄型保険はどのような方が契約していますか?
弊社のお客さまの多くは30代〜50代の駐在員のお客さまです。続いてタイ永住予定の現地採用の方、最近は事業売却や仮想通貨などの含み益などでタイへ移住される方のご契約も増えてきました。
オンライン上で弊社の存在を知ってご連絡をいただく方も多いですが、会社の同僚やご友人などのご紹介、既に契約されているお客様からの2つ目以降のご契約のお問い合わせが現在も変わらず多いです。
現在の資産や目的、将来的なプランなどによって最適な資産運用の方法というのは異なります。
GLOBAL SUPPORT(THAILAND)が考える資産運用は、本業により集中するための補完です。
そのための手段の一つとして、日本やタイの預金口座に置いたままの資金を活用した貯蓄型生命保険をご提案させていただいています。
タイ在住中の資産運用についてお気軽に弊社の無料個別相談をご利用ください。
Global Support (Thailand) Co.,Ltd.
代表 久米直也
Global Support (Thailand) Co.,Ltd.は、タイ駐在・在住日本人の方に対して資産運用のサポートをしております。
タイ駐在・在住中における資産運用についてメリットとデメリットを正しくお伝えし、経済面・精神面での豊かさ、果ては社会の発展の実現に向けてお役に立てれば幸いです。