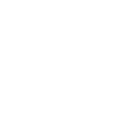家族にとって、帰国後の子どもの教育(進路)は心配ごとの一つです。どの学校に「いつ、どのようにして入学・編入」すればよいのでしょう?
- 本帰国が決まったら、まずやる事!
- 帰国後に通う学校の選び方・探し方
- 保育園・幼稚園への入園&中途入園
- 入学・編入学に必要な書類(※一例)
- 保育園・幼稚園探しの注意点
- 小学校への入学&編入学
- 入学・編入学に必要な書類(※一例です)
- 国立・私立・公立小学校への入学・編入学
- 公立中学校への入学・編入学
- 必要な書類と手続き(※一例)
- 私立中学校への入学&編入学
- 出願資格・条件
- 試験時期
- 出願書類
- 帰国生入試で高校に入る方法
- 出願書類・作成上の注意
- 出願資格
- 選考方法
- 滞在時からの準備
- スケジュール
- 受験の準備
- 812人の帰国生に聞いた学校生活のリアル
- 本帰国後の子どもの生活
- 学生寮
- 入寮前にチェックすべきこと
- 寮生活のアレコレ
- 保護者に出来る帰国前後のグッドアクション
- 本帰国体験記
本帰国が決まったら、まずやる事!
通っている学校や塾などに本帰国の旨を伝える
本帰国が決定して帰国日も決まったら、まずは子どもの通っている学校や担任の先生へ報告しましょう。その後、退学関係の書類を学校へ提出し、学費の返金対応などを行います。塾や習い事に通っている場合も同じく終了の手続きが必要です。
帰国後に入学・編入学する幼稚園や学校の情報収集
帰国時期や居住する予定の地域が確定したら、幼稚園や学校の情報収集をしましょう。海外からでも参加できるオンライン説明会を実施しているので、参加するのもおすすめです。
また、ほとんどの幼稚園や学校へ入学するための申し込みは、帰国後でないと受け付けてもらえません。電話での問い合わせは可能なので、入学条件や必要書類について事前に確認しておくと安心です。
入学試験・編入学の準備
公立学校の場合は入学・編入学試験を実施しないことが多いですが、私立の学校や高校の場合は入学・編入学試験を受ける必要があります。試験内容は学校ごとで異なりますが、帰国するまでの間に試験勉強や対策をしておきましょう。
帰国後に必要な書類
日本の学校へ入学・編入学するときに必要な書類は帰国前に早めに準備しましょう。特に在学証明書や卒業証明書は現地で通っていた学校での発行が必要となるので注意しましょう。
- ・在学証明書(現地で通っていた学校のもの)
- ・卒業証明書(現地で通っていた学校のもの)
- ・成績証明書(現地で通っていた学校のもの)
- ・推薦書
※学校ごとで提出書類は異なります
帰国後に通う学校の選び方・探し方
1.子どもと学校の相性を見極める
日本の学校と海外の学校では授業の進め方やカリキュラム、学校生活のルールなども大きく異なります。学校を選ぶうえで大切なことは、子どもと学校の相性を見極めることです。そのためには、子どもの学力、性格、家庭の教育観などに合った学校を選ぶことが重要になります。
- 学校の校風
- 教育方針
- カリキュラム
- 帰国生の在籍者数
- 帰国生の受け入れ体制
- 部活動や学校行事
- 卒業生の進路
- 施設設備
- 通学時間
2.学校の特色を調べる(公立・私立・国立の特色)
公立の場合、中学校ではほぼ同一の教育が行われますが、中高一貫校、公立高校では国際教養科、国際総合科などが設置されています。入学後の留学制度や外国人教師による外国語教育に力を入れています。
私立や国立の場合、各校それぞれに特色があります。
例えば、帰国子女のほか外国籍の生徒が多い学校などでは英語以外の科目も英語で授業を行い、外国語としての英語をより実現するための英語教育を実施しています。
3.一時帰国中に体験入学や学校説明会に参加してみる
夏休みなどの長期休みに日本へ一時帰国する際、実際に日本の学校に体験入学したり、学校説明会に参加してみるのもおすすめ。短期間でも日本の学校に通い、学校生活を体験することで、日本の学校の雰囲気を感じることができ、子どもたちにとっても良い刺激になります。